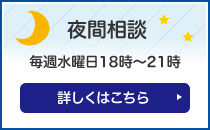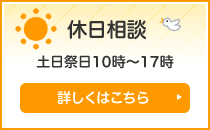- HOME
- 素因減額
素因減額
 【目次】
【目次】1 加齢変性、経年性変化等で素因減額を主張された場合の対処法
2 身体的素因について
3 心因的要因について
素因減額とは、損害拡大に寄与している被害者側の要因がある場合に、それを素因と呼び、素因を考慮して責任を減じたり、損害額を金銭的に減額することをいいます。
裁判例においては、身体的素因と心因的要因とで、扱いが異なっていますので、以下、具体的に説明します。
加齢変性、経年性変化等で素因減額を主張された場合の対処法
加害者の保険会社が、MRIやレントゲンの画像に加齢変性や経年性変化が見られることを理由に、素因減額を主張してくることが散見されます。
加齢変性や経年性変化は、年を取れば誰にでも見られるものです。
そのため、加齢変性や経年性変化があるからといって、直ちに素因減額が認められることにはなっていません。
後述のとおり、東京地裁でも「当該年齢の人間に通常みられる加齢性の変化」は素因減額の対象とはしていません。
年齢相応の範囲を超えて初めて、素因減額の対象となりうるのです。
(ただし、年齢相応の範囲を超えたら直ちに素因減額が認められるというものでもありません。注意が必要です。)
もっとも、問題となっている加齢変性について、ただ「年齢相応のものだから、素因減額の対象にはならない」と主張しても、加害者の保険会社は、年齢相応を超えているから素因減額が認められると主張してきて、水掛け論になってしまいます。
そこで、当事務所では、加齢変性や経年性変化が問題となる場合には、放射線診断専門医に画像鑑定を依頼することが多いです。
画像鑑定によって、加齢変性や経年性変化が年齢相応であることが明確になれば、加害者の保険会社も譲歩することが多いです。
加齢変性、経年性変化等で、素因減額を主張された場合には、お気軽にご相談下さい。
身体的素因について
身体的素因を理由とした素因減額に関して、重要な最高裁判例が2つあります。最判平成4年6月25日
最高裁は「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができる」と判示して、50%の素因減額をした東京高裁の判断を支持しました。
ここで、極めて重要なことは、「しんしゃくすることができる」とされていることです。
「必ずする」とはされていません。
つまり、加害行為と被害者の罹患していた疾患がともに原因となって損害が発生した場合でも、必ず素因減額がなされるわけではないということです。
また、加害者に損害の全部を賠償させても公平を害さないような場合には、素因減額はなされないとも読むことができます。
例えば、事故が極めて甚大な場合には、被害者の罹患していた疾患が多少影響していると思われても、素因減額されない場合がありうると読み取れます。
最判平成8年10月29日
最高裁は「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない」と判示して、40%の素因減額をした福岡高裁宮崎支部の判決を破棄しました。
素因減額の要件
これら2つの判例からは、素因減額の要件として、
『身体的特徴を超える「疾患」といえる状態にあること』
が必要であるということが分かります。
これが、身体的素因を理由とする減額についての最高裁の考え方の基本です。
身体的素因についての東京地裁の考え方
以上のような判例の考え方を受けて東京地裁では、概ね以下のような考え方が採られているといわれています。
①事故の前から存在した被害者の疾患が損害の発生又は拡大に寄与していることが明白である場合には、賠償すべき金額を決定するに当たり、当該疾患をしんしゃくすることができる。
②加齢的変性については、事故前に疾患といえるような状態であったことが認められない限り、しんしゃくしない。当該年齢の人間に通常みられる加齢性の変化ないし個体差の範囲内の加齢性の変化を理由に減額するのは相当ではない。
③病名が付けられるような疾患には当たらない身体的特徴であっても、疾患に比肩すべきものであり、かつ、被害者が負傷しないように慎重な行動を求められるような特段の事情が存在する場合(たとえば極端な肥満)にも、当該身体的特徴をしんしゃくすることができるが、極めて例外的な場合に限られる。
疾患別の素因減額
▶ 後縦靱帯骨化症
▶ 椎間板ヘルニア
▶ 脊柱管狭窄
▶ 骨粗しょう症
心因的要因について
心因的要因を理由とした素因減額に関して、重要な最高裁判例が2つあります。最判昭和63年4月21日
最高裁は、追突事故により、外傷性頭頸部症候群等の診断を受けて、10年以上入通院治療を受けた被害者について、「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる」として、40%の素因減額をした原審の判断を支持しました。
最判平成12年3月24日
最高裁は、長時間残業が1年余り継続した後、うつ病に罹患して自殺した被害者について、「企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきものということができる。しかも、使用者又はこれに代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う者は、各労働者がその従事すべき業務に適するか否かを判断して、その配置先、遂行すべき業務の内容等を定めるのであり、その際に、各労働者の性格をも考慮することができるのである。したがって、労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心因的要因としてしんしゃくすることはできない」として、30%の素因減額をした原審の判断を破棄しました。心因的要因についての東京地裁の考え方
以上のような判例の考え方を受けて東京地裁では、概ね以下の要素を満たす場合には、当該心因的要因を考慮することができるという考え方が採られています。①原因となった事故が軽微で通常人に対して、心理的影響を与える程度ではない
②愁訴に見合った他覚的な医学的所見を伴わない
③一般的な加療相当期間を超えて加療を必要とした場合
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.